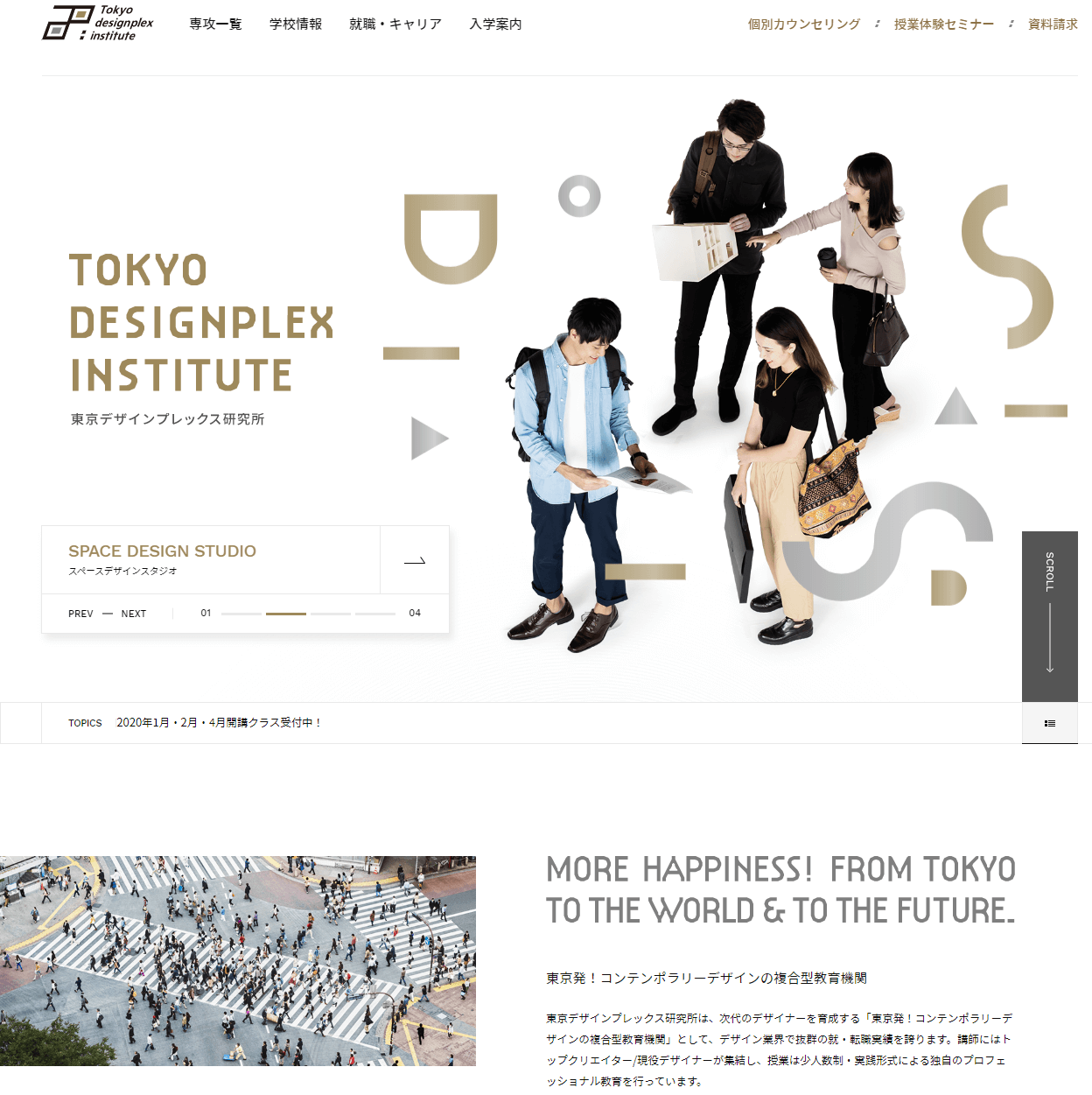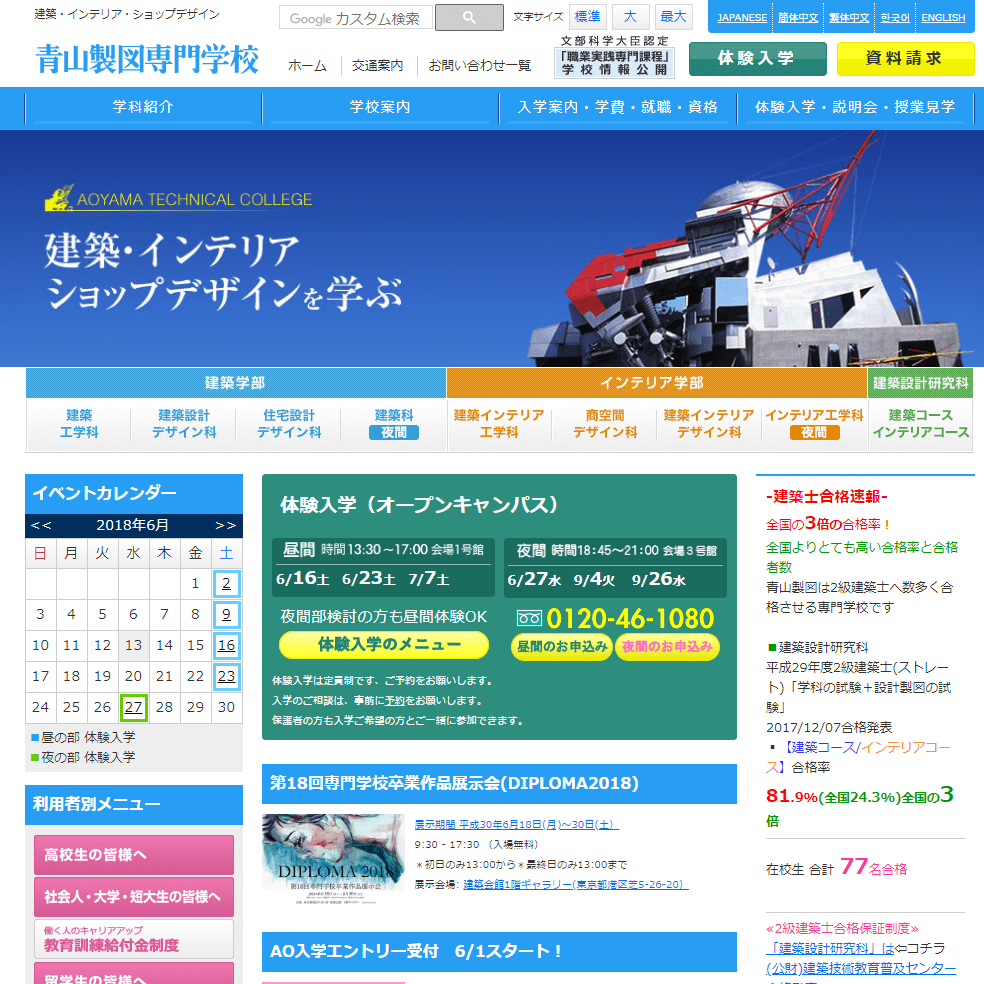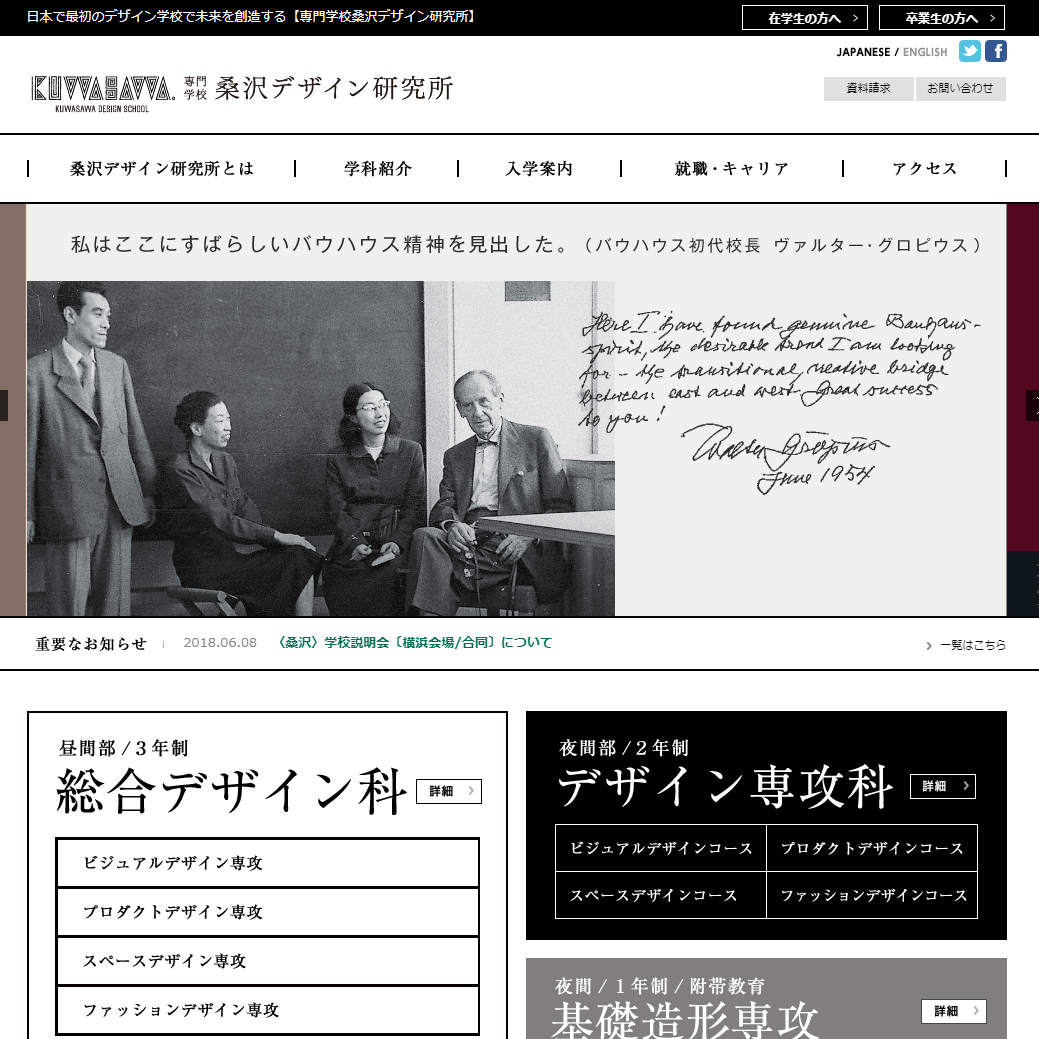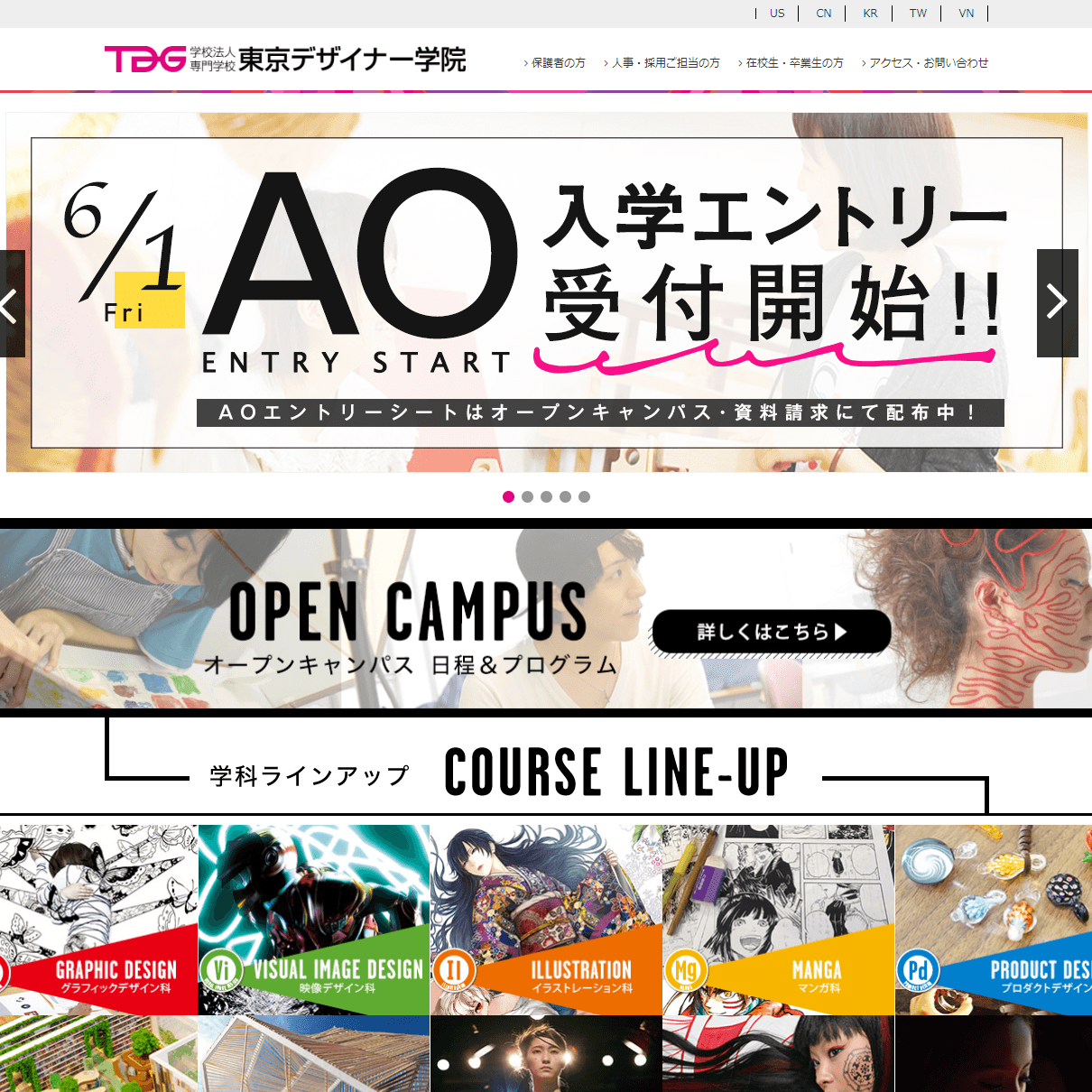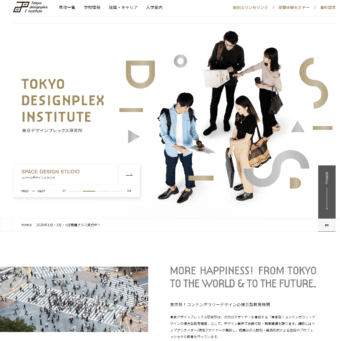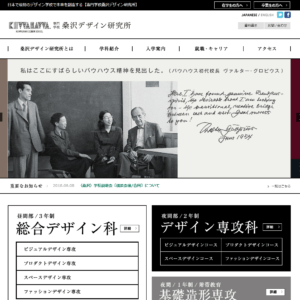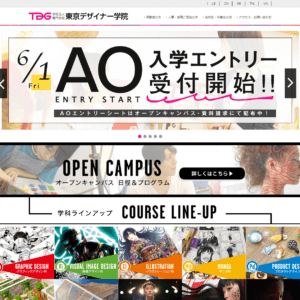空間デザイナーとして働くなら就職とフリーランスどちらがおすすめ?

空間デザイナーとして働くためには、就職とフリーランスで働くことの2通りの働き方があります。どちらの働き方でも、空間デザイナーとして活躍できますが、企業に就職することと、フリーランスで働くことにはどのような違いがあるのでしょうか。そこで今回は、空間デザイナーの仕事の流れや、就職とフリーランスの違いなどを解説します。
空間デザイナーの仕事の流れ
空間をデザインするためには、どのような流れで進んでいくのでしょうか。ここでは、空間デザイナーの仕事の流れを解説します。
依頼者から依頼内容のヒアリング
依頼を受けたら、依頼者と依頼内容のヒアリングを実施。どのようなイメージで空間を演出したいのか、予算はどのくらいで納期はいつか、依頼者の要望など細かく聞いて、イメージを共有します。
イメージを共有したらデザイン案の作成
何度も依頼者とヒアリングをして、イメージの共有ができたらデザイン案の作成です。ラフスケッチや図面で簡単に完成時をデザインしたら、CGや模型を作製して、より具体的な完成デザインで、プレゼンテーションを実施します。
インテリアのセレクト、施工図作成
必要なインテリアや照明などをセレクトし、手配しておきます。また、施工現場で作業を行うための施工図を作成。
施工開始
施工は業者が行うので、施工業者を選定したら施工開始です。空間デザイナーは、イメージ通りの施工が進んでいるか、現場を訪問しチェックします。イメージとのズレが生じていれば、指示を出し修正していきます。
引渡し
施工が完了したら引渡しです。万が一のトラブルにしっかり対応するように、アフターフォローも行います。
空間デザイナーとして働くなら就職とフリーランスどちらがおすすめ?
空間デザイナーは、就職する場合とフリーランスで働く場合では、どのような違いがあるのでしょうか。ここでは、就職とフリーランスの違いを解説します。
就職する場合
空間デザイナーの就職先は、空間デザイン事務所や建築関連の事務所が多いです。就職をするメリットは、空間デザインをするノウハウを学べる事です。未経験者が空間デザイナーとしての実績を積むためには、上司や先輩から仕事の仕方や流れを学び、他業種とチームを組んで実践経験を重ねながら、人脈を広げることができます。
フリーランスの場合
フリーランスの空間デザイナーは、自分が担当した案件はそのまま自分の収入になることや、自分で働きやすい時間に仕事ができるなど、多くのメリットがあります。しかしその反面、実力や人脈がないと、仕事の依頼が来ないということにもなりかねません。
そのため、独立する前に、多くの実践経験を積んで、自身の評価を高めることが重要です。
まずは空間デザインに関するスキル・知識を身に着けよう!
空間デザイナーになるためには、まず空間デザインに関するスキルや知識を身につけなければなりません。ここでは、空間デザインを身につける方法を解説します。
専門学校で学ぶ
空間デザイナーになるために、専門学校で空間デザインに関するスキルや知識を学んだ人は多いです。専門学校では基礎的なことから学べますし、わからないことがあっても講師に質問して解決できるので、効率よく勉強が進みます。また、即戦力として活躍できるように、スキルを身につけるカリキュラムが組まれているため、就職先でも安心して仕事ができるでしょう。
独学で身につける
独学で知識を身につけ、空間デザイナーになることもできます。自身でテキストや参考書を購入し勉強したり、通信講座で専門的な知識を学んだりしながら習得していくことになるでしょう。しかし、知識を学ぶことはできても、実践的なスキルを身につけることができないので、空間デザインを手掛けている企業でアルバイトをしながら、習得する必要があるかもしれません。
まとめ
空間デザイナーの仕事の流れは、まず依頼者から依頼内容のヒアリングをします。次に、イメージを共有しデザイン案の作成後、インテリアのセレクトや施工図の作成です。その後、施工を開始し完成したら、引き渡して完了です。就職して働くメリットには、空間デザインをするノウハウを学べる事があり、実践経験を積みながら人脈を広げることができます。フリーランスで働くメリットは、高収入や働く時間を選べることがありますが、その反面実力や人脈がないと、仕事の依頼が来ないかもしれません。スキルや知識を身につけるためには、専門学校で学ぶ方法と独学で身につける方法があります。